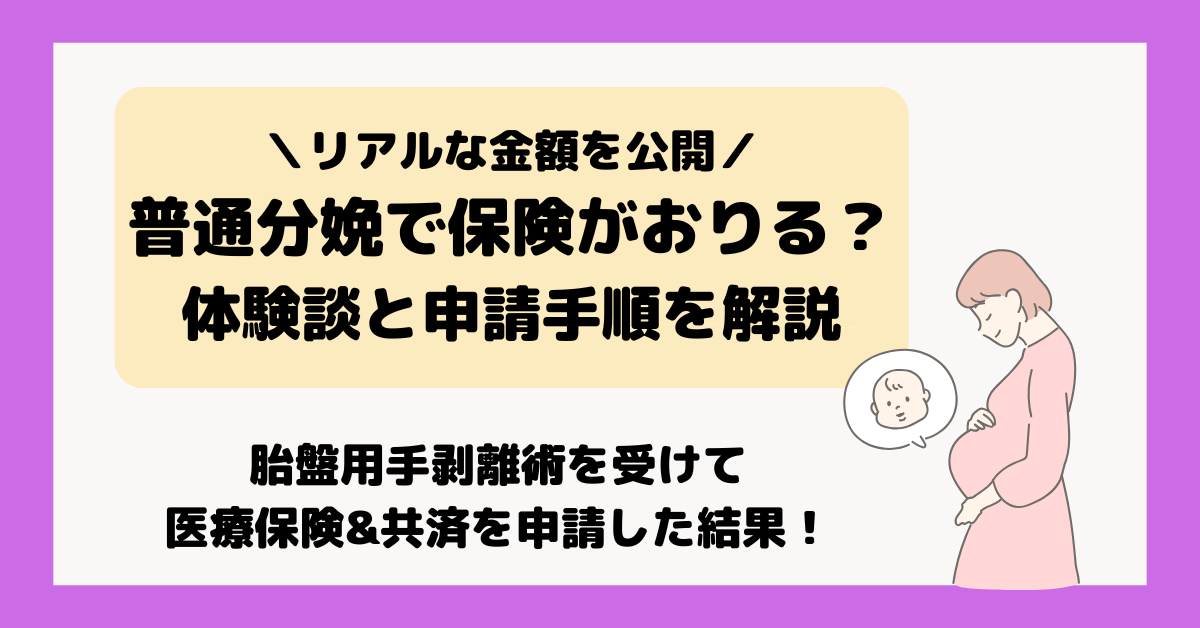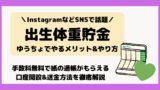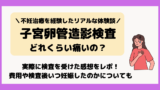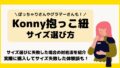帝王切開であれば民間の医療保険が申請できるというのは知られていますが、普通分娩だった場合は保険金が申請できないと諦めていませんか?
実は、普通分娩(自然分娩)でも民間の医療保険が申請できる場合があるんです!
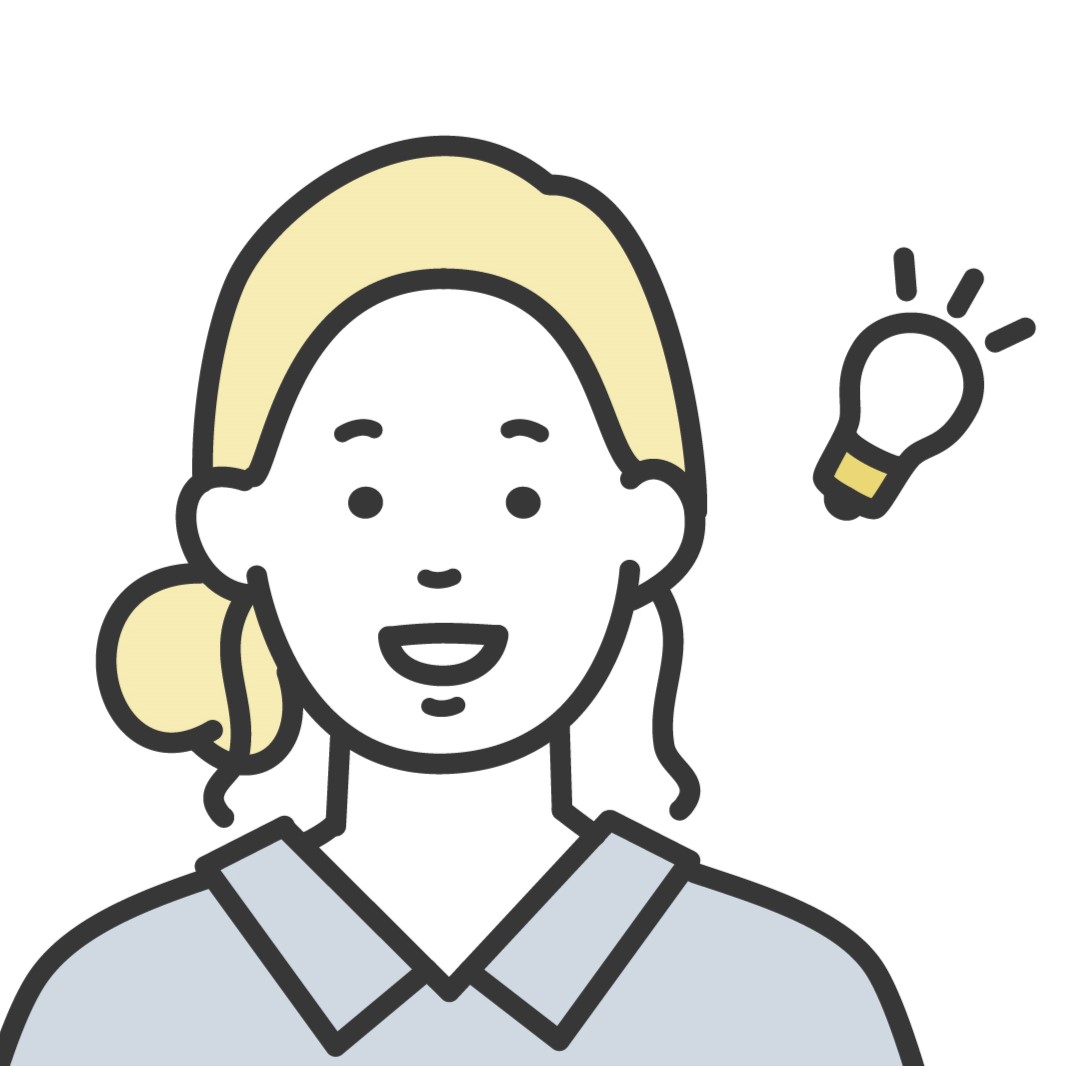
私は普通分娩で第一子を生みましたが、保険金を受け取ることができました。
この記事では、普通分娩でも保険がおりる!?胎盤用手剥離で民間の医療保険と共済に申請した結果と金額を公開します。
※この記事は筆者個人の体験をまとめたものです。保険がおりるかどうかは保険会社が判断するため、症例ごとに異なります。
普通分娩でも保険がおりるって本当?
現在の日本の制度では、普通分娩(自然分娩)は保険適用の対象外です。
そのため、基本的に出産で民間の医療保険を申請することはできません。
しかし、分娩前後に何らかの医療行為が加わり、異常分娩と診断された場合は民間の医療保険がおりる可能性があるのです。
異常分娩とは
- 帝王切開
- 吸引分娩や鉗子分娩などの器械分娩
- 早産分娩
- 骨盤位分娩
などが挙げられます。
帝王切開で出産した場合はわかりやすいですが、経腟分娩の場合は自身が異常分娩として保険の対象になるかどうかどうかわかりづらいですよね。

筆者は出産時、なかなか胎盤が出なかったため胎盤用手剥離を受けましたが、病院から保険についての説明はありませんでした。
自身の出産で医療保険が申請できるのかどうかを見極めるポイントは病院から貰う医療報酬診療点数表に保険適用の点数があるかどうかです。
しかし、保険適用の欄に点数があるからといって100%保険金を受け取れるわけではありません。
異常分娩かどうかを判断するのは医療機関で、保険会社は診断書等の提出書類を見て判断します。
医療報酬診療点数表に保険適用の点数があったとしても、医療機関や保険会社の判断によっては保険金を受け取ることができないので注意しましょう。

診断書等の提出書類や判断基準は保険会社や契約状況によって異なるので、自身が加入している保険会社に確認してください!
胎盤用手剝離術で保険申請をした結果と金額

私は後産処置の際に胎盤用手剥離術(K902)という処置を受けました。
胎盤用手剥離とは、子宮内に残った胎盤を医師が手を入れて子宮壁から剥がす処置です。
私の場合は手術室ではなく分娩室で胎盤用手剥離術が行われたため、自分が術式を受けていることを認識していませんでした。
病院から手術をしたという説明があったのかもしれませんが、産後で放心状態のため覚えておらず…。(コロナ禍のため主人は院内に入れませんでした。)
後程、病院から貰った領収書と診療報酬明細表(レセプト)を見て手術の欄に点数があり健康保険が適用されていることに気が付いたのです。

母子手帳には自然分娩と記入されていたのでとても驚きました!
医療保険と共済の申請ができるかも?
産院から受け取った領収書と診療報酬明細表を見て、手術に点数があると気付いた私は、もしかしたら医療保険がおりるかも…と考え、加入していた2つの保険会社に電話で確認してみることに。
C共済の窓口に術式名を伝えると「手術として保険が請求出来る」とのこと。
羊のキャラクターでお馴染みの医療保険の窓口に相談すると「術式名では判断できないので、診断書が必要」とのことでした。
2つの保険会社とも診断書が必要とのことでしたので、病院で診断書を取り寄せ請求書類を送付しました。
病院で診断書を書いてもらうには、お金が必要で、私の場合は約4,000円かかりました。
病院の診断書を受け取るまで、確か2週間ほどかかったと思います。

事前に確認のうえ、病院には1枚だけ書いてもらってコピーして提出しました。
無事に入金!金額に驚き
保険会社や共済が指定した保険金請求書や病院に書いてもらった診断書など書類を揃えて送付した結果…。
2つの保険とも、手術+入院(全日)保険がおりました!!
金額にすると、合計13万円ほどです。
出産育児一時金では出産費用を全てカバーすることはできず、手出し15万円ほど支払いをしていたので、とてもありがたい結果となりました。
4泊5日の入院は健康保険ではなく自費でしたし、手術分のみの金額を受け取れるのだろうと思っていましたので、入院全日分医療保険がおりたのは本当にびっくりです。
女性向け特約を付けていた保険は支払い金額に上乗せがあったので本当に助かりました。
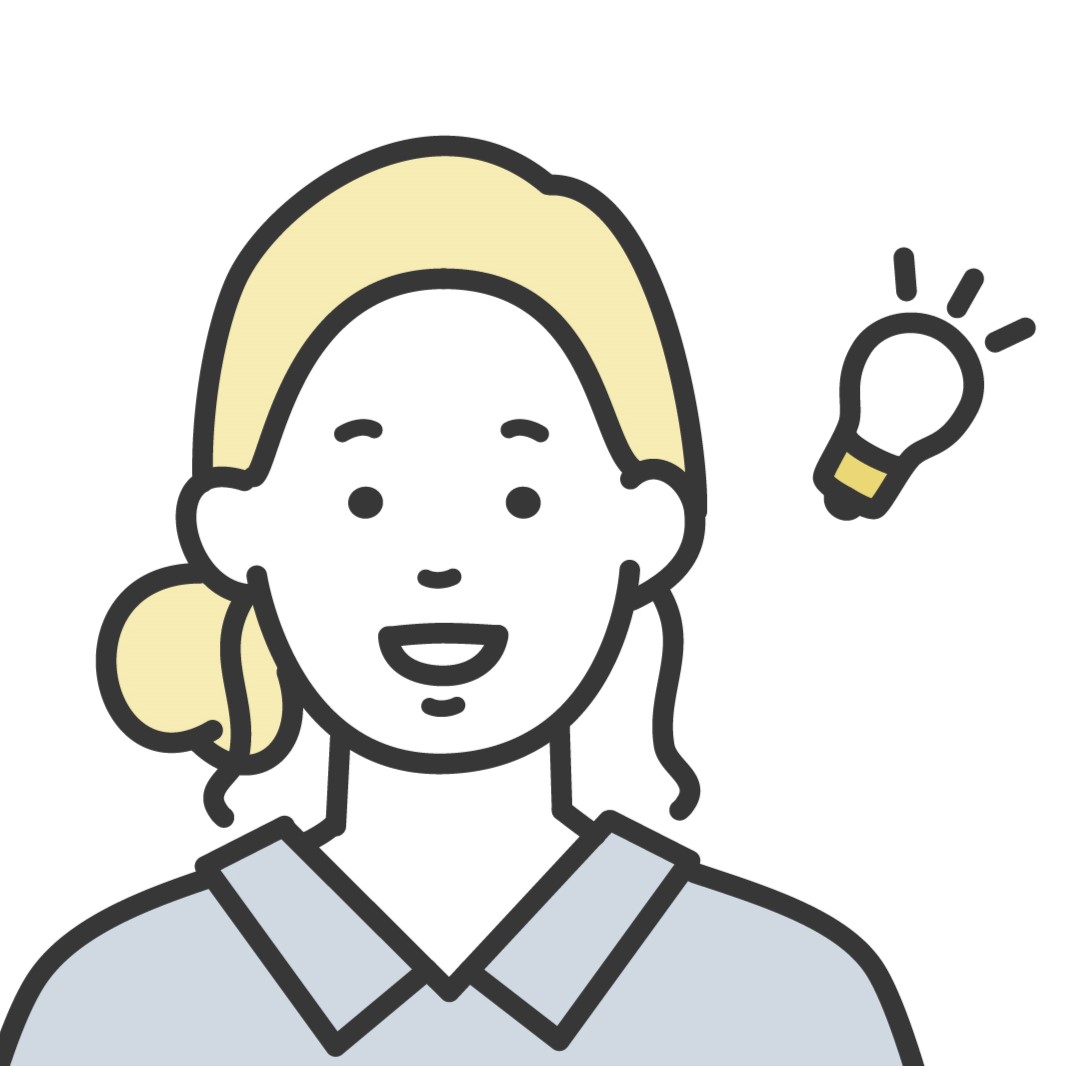
保険に加入していて良かったです!
もしかしたら保険金を受け取れる?と思った時の手順
私の経験を読んだ人のなかに、”もしかしたら私も保険金を受け取れるかも!?”と思った人もいるのではないでしょうか?
病院から説明があると分かりやすいですが、特に何も説明がないと分かりづらいですよね。

私の場合、病院から保険などについての案内はありませんでした。
普通分娩であっても、異常分娩扱いの場合は民間の医療保険や共済の保険金(共済金)を受け取れる可能性があります。
ここからは出産後に保険金を請求できるかどうかのポイントと手順はこちらです。
①病院からの領収書&診療報酬明細表(レセプト)を確認する
②保険会社に問い合わせる
③請求書類を揃える
④完了(保険金を受け取る)
異常分娩かどうかを判断するのは医療機関で、保険会社は診断書等の提出書類を見て判断するため、症状が同じであっても確実に保険金が受け取れるとは限りませんのでご注意ください。
①病院からの領収書&診療報酬明細表(レセプト)を確認する
分娩で保険金を請求できるかどうか迷ったら、まずは病院からもらった領収書と診療報酬明細表(レセプト)を確認しましょう。
診療報酬明細表とは、医療機関が健康保険組合に医療費を請求するために、行った処置や使用した薬剤等を記載した明細表のことでレセプトとも呼ばれているものです。
レセプトには、処置、検査、手術など項目ごとに点数が記載されており、保険内なのか自費扱いなのかもわかるようになってます。
手術の欄に点数の記載があったり、本来保険が適用されないはずの分娩費用や入院が自費ではなく保険内で計算されていたりする場合、保険を申請できる可能性があります。
②保険会社に問い合わせる
保険金・給付金を受け取れるかも?と思ったら、加入している保険の契約内容を確認し、保険会社へ連絡をしましょう。
オンラインや電話など、請求方法は保険会社により異なります。
その場で受け取りができるかどうか教えてもらえる場合もあれば、不明の場合もあります。
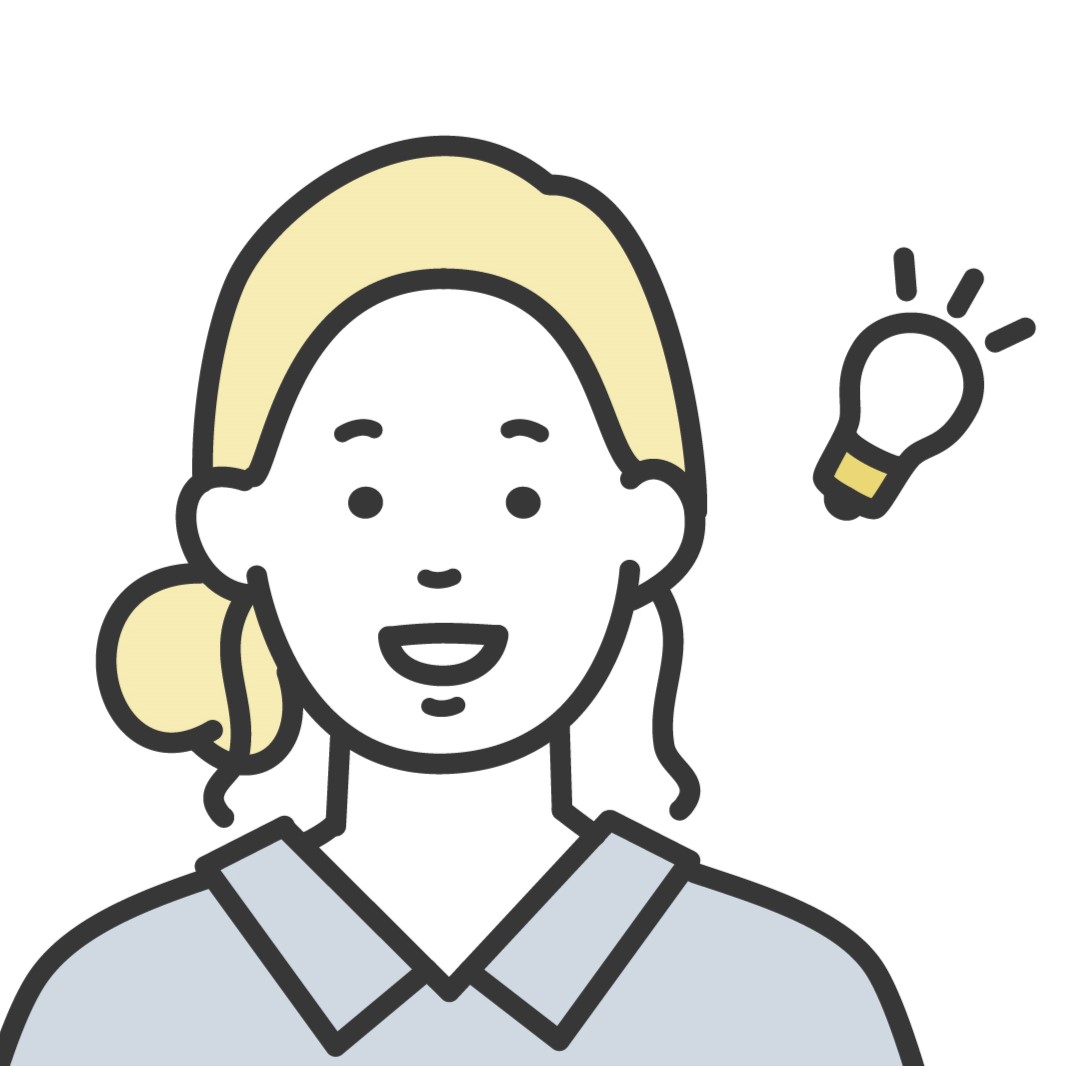
実際に私が2社に問い合わせた際、1社から『レセプトの手術蘭に点数があるのなら保険金を受け取れる』と回答をいただき、もう1社からは『診断書など確認しないと分からない』といった回答でした。
③請求書類を揃える
保険の申請・請求をすることになったら、保険会社所定の書類を揃えて提出します。
用意する書類は、請求書や診断書、病院の領収証などです。
診断書は不要な時もありますし、病院のものではなく保険会社指定の形式での診断書提出が必要なことも。
先走って用意せず保険会社の指示を待ってから書類をそろえるのがおすすめです。
保険会社は請求書類を確認して判断しているので、書類を送ったからといって確実に保険金を受け取れるわけではないので注意しましょう。
④完了(保険金を受け取る)
書類を送付したら、手続きは完了です。
後日、保険会社より結果が通達されますので、内容を確認しましょう。
保険金を受け取れる場合の保険金・給付金は受取人指定の金融機関口座に振り込まれます。
普通分娩でも保険はおりる?まとめ
現在の日本では出産は公的な保険の適用外となっているため、普通分娩では民間の医療保険や共済を請求することはできません。
しかし、普通分娩だと思っていても実際には異常分娩として扱われている場合があり、民間の医療保険を請求できることがあります。
保険が請求できるか見分けるポイントは、診療報酬明細表(レセプト)の手術や入院の欄に保険適用の点数があるかどうか。
保険会社にもよりますが遡って請求できる場合もありますので、一度ご自身の領収証やレセプトを確認してみてくださいね。
今回は一例として、胎盤用手剝離術で保険がおりた筆者の体験談をお伝えしました。
ご自身の分娩で民間の医療保険や共済が請求できるかも…と迷っている人は、ぜひ参考にしてください。

あくまでも筆者の経験であり、胎盤用手剥離術は必ず医療保険がおりるという話ではないので注意してくださいね。